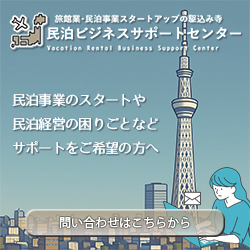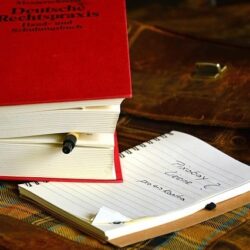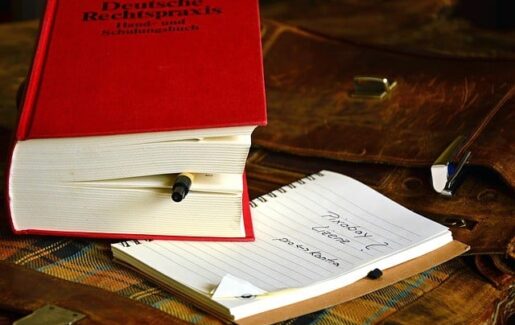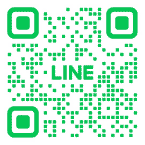こんにちは。民泊ビジネスサポートセンター、代表の酒井です。
本ブログでは、「民泊ビジネスのコンパス」となる情報を発信していきます。
現代はとても便利な世の中で、インターネットで何かを調べようと思うと、大量に情報が出てきます。ただその分、いつの情報か、その情報元が信頼できるかなど情報を選択していかないと誤った情報に出会うという状況であるとも言えます。わたしも日々その点を考慮して調べ物をしています。前回から続いて、民泊ビジネスの入口である旅館業法許可を理解していきますが、この理解でも、やはりインターネット等で情報を確認する際は、情報の選択が重要になります。
旅館業法手続きについて数々のお問い合わせをいただいてきましたが、ある傾向に気づいたことがあります。それは、ある程度事前に調べをしてお問い合わせいただいたとお見受けする方が「民泊をやりたいのだけど簡易宿所(簡易宿泊所)の許可が取れるか知りたい」というように「民泊=簡易宿所の許可」というイメージでお話される方が一定数いらっしゃることです。
事前にご自身でお調べいただいてのお問い合わせは当方としてはとてもありがたい反面、誤解がある場合は、その誤解を解きほぐし改めて理解を進めていただくという形となります。この例もそうなるのですが、これには明確な原因があります。
この原因を通して、簡単に旅館業法許可の直近の歴史をお伝えしていこうと思います。
直近と書いたのは、旅館業法はとても古い法律で、前身から考えると明治時代、旅館業法としては戦後間もない昭和時期にできた法律ですので大変長い歴史があるからです。
実は現在の1棟貸し民泊の増加には、直近の旅館業法の改正が大きく影響しています。
その改正というのは俗にいう民泊元年2017年-2018年にありました。
画期的な改正で、それまで1グループに1客室を提供する形で旅館業を行うには客室数をホテルは10室以上、旅館は5室以上でなければならないとしていたものを廃止し、客室1室でも可能とするというものでした。
これにより、現在の1棟1グループ貸し形態の宿が合法に営業できるようになりました。
ではこの改正前はというと、ホテル営業・旅館営業とは異なる種別である「簡易宿所」営業のみが客室1室でも営業が可能という状況だったのです。(下宿営業については省略)
ここに、「民泊=簡易宿所の許可」というイメージの原因に繋がる点があります。
要するに、この改正前に1室の宿泊業を営むには「簡易宿所」営業しか選択肢がなかったということになります。ですのでその当時のwebページや書籍などを見ると「民泊=簡易宿所の許可」という記載が多数あります。これがお問い合わせいただいた方の頭の中に残り、「簡易宿所の許可が取れるか知りたい」という表現になったのだと考えられます。日々変わっていく世の中にあわせて法律や規制もどんどん変化していきます。この例も、法規制の変化により定義が変わっている語句(ここでは「民泊=簡易宿所」)を使用してしまい誤解、誤認を生じるという例になると思います。ちなみに旅館業法の役所、保健所職員とこの話をしたところ、職員の方に共感いただいたことがあります。その職員の方は、実際に窓口に来た一般の方が、簡易宿所をやりたいといっているので簡易宿所営業の説明をしたら、そんな営業の仕方をしたいわけではないとなることがよくあるので、先にどのような営業をしたいですかと質問するようにしているということです。
日々の変化に対応することは簡単ではないですが、確実な情報を得て、変化を好機にしていきたいものです。
次回から今回登場している「旅館・ホテル営業」「簡易宿所営業」などの旅館業法の営業種別について解説していきます。 このブログを通して、多様な選択肢から自身の思い描く、どこにも同じもののない「オリジナルの宿」を確立し実現していただければと思います。